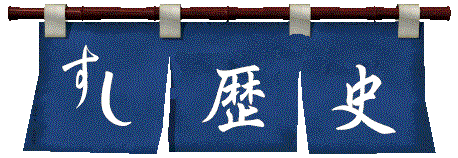
| 「寿司」正しくは「なれ寿司」は、保存食として東南アジアから中国へ、そして我が国へと伝えられたものです。寿司は、東南アジアの山間民族の間で行われていた魚の貯蔵方法で、初期の材料の多くは川ざかなにかぎられていたそうです。 |
| 我が国の寿司に関する最も古い文献は、1200年前のものであり、その中に「雑鮓」、「鮎貝鮓」といった文字が出ているといわれ |
|
|
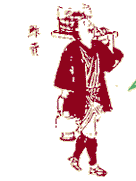 |
「寿司売り」と称して頭に手ぬぐいを被り、身綺麗な着付けで白木の箱を肩に担いで「寿司やー、こはだのうす寿司ぃー」と美声で売り歩いていたそうです。 このころの店の多くは、屋台形式で片流れの屋根を付け、前と両側に油障子を立て、その中でツケ台ににぎり寿司を置いて、立ち食い形式だったそうです。 現在でもにぎり寿司を、お好みで召し上がるお客様を「立ち」のお客様と呼ぶのは、このためです。 年代が進むに連れ、寿司店の店構えも現在のような体裁になってきました 現在のような「にぎり寿司」が現われたは、文政6年(1823)江戸、両国の与兵衛寿司の「華屋 与兵衛」の考案とされています |
 |